きゅうりは、家庭菜園の中でも比較的育てやすく、短期間で収穫できる人気の夏野菜です。しかし、いざ育ててみると「わき芽はどれを取ればいいの?」「摘芯って何?」「このタイミングで合ってるの?」といった疑問にぶつかる方も多いのではないでしょうか。特に「きゅうりの育て方とわき芽の管理」は、初心者がつまずきやすいポイントのひとつです。
このページでは、そんな悩みを持つ方に向けて、きゅうりの基本的な育て方から、わき芽の見分け方、摘芯のコツ、支柱の立て方まで、初心者でも実践できる方法を丁寧に解説しています。すべて実際の栽培経験や園芸の基礎知識に基づいてまとめているため、信頼性の高い情報として活用いただけます。
読み進めるうちに、「なるほど、こうすれば良かったのか」と納得できるポイントがきっと見つかるはずです。初めてきゅうりを育てる方はもちろん、過去に失敗したことがある方にも、もう一度チャレンジしたくなるような内容になっています。わかりやすく実践的な内容を心がけていますので、ぜひ最後までご覧ください。
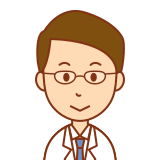
💡記事のポイント
- きゅうりの育て方の基本的な流れとポイントがわかる
- わき芽の見分け方と処理のタイミングが理解できる
- プランターや支柱の使い方など具体的な栽培方法が学べる
- 栽培時に避けるべき組み合わせやトラブル対策がわかる
きゅうりの育て方とわき芽の管理で収穫量をアップする方法

- きゅうりの育て方で初心者が押さえておきたい基本ポイントとは?
- プランターでのきゅうりの育て方と失敗しないコツ
- きゅうりの支柱を一本立てで設置する方法とそのメリット
- 小学生でもできる!きゅうりの育て方をやさしく解説
- きゅうりの近くに植えてはいけない野菜とその理由
- きゅうりの芽とわき芽の違いを正しく理解しよう
きゅうりの育て方で初心者が押さえておきたい基本ポイントとは?
きゅうりを初めて育てる人にとって、最初に意識すべきなのは「きゅうりが思った以上に成長が早く、手入れの頻度が高い野菜だ」という点です。気温や湿度の影響を強く受けるため、毎日の観察と、適切なタイミングでの水やりや管理が必要になります。
まず、植え付けの時期ですが、気温が安定する5月上旬から中旬が適しています。寒さに弱いため、霜の心配がある地域では遅霜が完全になくなってから植えるようにしましょう。次に、きゅうりは日当たりの良い場所を好みます。半日陰では生育が遅れ、実つきも悪くなるため、少なくとも1日に5~6時間は直射日光が当たる場所を選んでください。
土づくりについても見落とせない要素です。きゅうりは根の張りが浅いため、排水性と保水性のバランスが重要になります。市販の野菜用培養土でも栽培可能ですが、できれば堆肥や腐葉土を加えておくと、根の張りがよくなり、収穫量も増えます。
また、水やりの頻度にも注意が必要です。梅雨時期を除いて、基本的には土の表面が乾いたらたっぷり与えるようにします。特に夏場は朝と夕の2回に分けて水やりをすると、根が傷まず安定した成長を促せます。
注意点として、初心者がやってしまいがちなのが「追肥を早くしすぎる」ことです。肥料は根がしっかり張ってから与えることが大切で、目安としては定植後2〜3週間後、つるが伸び始めた頃から少しずつ施していくとよいでしょう。
このように、きゅうりの育て方では「観察・タイミング・環境」が特に重要です。これらを理解していれば、初心者でもしっかりと収穫を楽しむことができます。
プランターでのきゅうりの育て方と失敗しないコツ
家庭菜園初心者が手軽にきゅうり栽培を始めるなら、プランターは非常に有効な選択肢です。しかし、露地栽培とは異なる制約があるため、いくつかの注意点を踏まえる必要があります。
まず、使用するプランターのサイズですが、深さ30cm以上・容量20L以上の大型タイプを選ぶことが基本です。きゅうりは根を広く浅く張る性質があるため、深さだけでなく「広さ」も必要です。狭いプランターでは水分や養分が不足しがちになり、病害虫のリスクも上がってしまいます。
土については、市販の野菜用培養土を使えば問題ありませんが、水はけが悪いと根腐れを起こしやすくなります。底に鉢底石を敷いたうえで、通気性のある土壌環境を整えてください。また、設置場所は必ず日当たりと風通しが良い場所を選ぶようにします。特にベランダで育てる場合、壁際に置いてしまうと風が抜けず、高温多湿で病気が出やすくなるため注意が必要です。
水やりについては、プランター栽培ではとても重要なポイントになります。土の量が限られているため、乾燥しやすく、水切れが生長不良の原因になることもあります。目安としては、夏場は1日2回、朝と夕方にたっぷりと水を与えると良いでしょう。
肥料の与え方にも工夫が必要です。プランターでは肥料分が流れやすいため、定期的に追肥を行うことが求められます。液体肥料であれば週1回、粒状の肥料であれば2週間に1回を目安にしてください。ただし、与えすぎると葉ばかり茂って実がつかなくなることもあります。
このように、プランターでのきゅうり栽培は管理のしやすさというメリットがある一方で、水やりや養分管理に気を配る必要があります。失敗しないためには、限られた環境の中でどれだけ最適な条件を保てるかがカギになります。
きゅうりの支柱を一本立てで設置する方法とそのメリット
きゅうり栽培では、つるが伸びていく特性に合わせて支柱を立てるのが一般的です。その中でも「一本立て」と呼ばれる方法は、特にスペースが限られている環境で有効とされています。設置の手間が少なく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。
設置方法としては、60cm〜150cmほどの支柱を1本、苗のすぐそばにしっかりと差し込みます。地面やプランターの底にしっかり固定できるよう、支柱の根元には支柱ホルダーや固定具を使うと安定性が高まります。あとは、成長に合わせて麻ひもなどで軽く茎を支柱に誘引していきます。
この一本立てには、整理整頓がしやすくなるという明確なメリットがあります。支柱が少ないぶん、風通しがよくなり、うどんこ病などの病害が発生しにくくなります。また、摘芯やわき芽処理などの手入れがしやすく、育てながら学びたいという初心者には向いている方法です。
一方で、デメリットもあります。一本立ての場合、支柱1本だけでつるの重みを支えるため、強風や大雨にはやや不安が残ります。このため、台風シーズンなどには補助の支柱を追加するなどの対策が求められます。また、2本立てや合掌式に比べるとつるを伸ばせる範囲が狭いため、収穫量もやや制限される傾向があります。
このように、一本立ての支柱設置は簡単かつコンパクトに始められる反面、環境の変化に対して注意が必要です。それでも、管理がしやすく初心者にも扱いやすい点は大きな魅力であり、小規模栽培やベランダ菜園には特に適しています。
小学生でもできる!きゅうりの育て方をやさしく解説

きゅうりは成長が早く、育て方のコツを覚えれば、小学生でも十分に収穫まで楽しむことができる野菜です。学校の自由研究にも向いていて、毎日の観察を通して植物の生長を身近に感じられる点が大きな魅力です。
最初に準備するのは、きゅうりの苗とプランター、そして野菜用の土です。ホームセンターなどで購入できる培養土には、あらかじめ必要な栄養が含まれているため、小学生でも扱いやすくなっています。プランターの大きさは、幅が30cm以上、深さも30cmくらいあるものを選ぶと良いでしょう。
苗を植えるときは、優しく土をほぐして根を傷めないようにします。苗の根元がしっかり土に埋まるようにして、軽く押さえて固定してください。植えたあとは、たっぷりと水を与えることを忘れないようにします。
水やりは毎日行う必要がありますが、特に暑い日は朝と夕方の2回がおすすめです。日中に水をあげると、気温が高いため土が熱くなりすぎて根にダメージを与えてしまうことがあるからです。観察を日課にすることで、土の乾き具合や葉っぱの様子に気づきやすくなります。
また、きゅうりはつるを伸ばしながら育つため、支柱を立ててあげることも大切です。つるが絡みやすいように、麻ひもなどでやさしく支柱に誘導しましょう。きゅうりの実がなると重みで折れてしまうこともあるため、茎が太くなってきたら支柱としっかり結び直して補強してあげると安心です。
失敗しやすい点としては、水やりのしすぎや日当たりの悪い場所での栽培があります。水が多すぎると根が腐ることがありますし、日光が不足すると花が咲かなかったり、実が小さくなったりすることがあります。
このように、きゅうりは毎日観察して変化を感じながら育てられる楽しい野菜です。世話をすればするほど元気に育つので、自由研究として写真や絵で記録を残すのもおすすめです。
きゅうりの近くに植えてはいけない野菜とその理由
家庭菜園では、複数の野菜を一緒に育てることがよくありますが、植物同士にも相性があり、近くに植えると生育に悪影響を及ぼす組み合わせも存在します。きゅうりの場合、特に注意すべき野菜がいくつかあります。
まず代表的なのが「じゃがいも」です。じゃがいもは地下茎で広がるように育つため、きゅうりの根のスペースを奪ってしまう恐れがあります。また、湿気を好む性質も似ているため、同じ環境下で育てると土壌中の水分が過剰になり、病気の原因となることがあります。
次に「トマト」も避けたほうがよいとされる野菜のひとつです。トマトときゅうりは育つ環境条件が異なります。トマトは乾燥気味を好みますが、きゅうりは水をたくさん必要とするため、水やりのタイミングや量に違いがあり、どちらか一方の生育を損なう結果になりやすいのです。
また、「ナス」や「ピーマン」などのナス科の野菜も注意が必要です。これらは土壌中の栄養を多く吸収するため、きゅうりと同時に育てると養分の取り合いが起きやすく、結果として双方の成長が鈍る傾向にあります。さらに、共通する病気(たとえば、青枯れ病)にかかるリスクも高まるため、近くに植えるのは避けたほうが安全です。
反対に、相性が良いとされる野菜も存在します。例えば、インゲン豆や枝豆などのマメ科植物は、根に共生する菌が土壌中の窒素分を補うため、きゅうりの育成を助けてくれます。
このように、きゅうりの近くにどんな野菜を植えるかは、病気の予防や栄養バランスを保つうえで非常に大切です。特に初心者の場合、トラブルが起きてから気づくケースも多いため、植え付けの前に相性を確認しておくと安心です。
きゅうりの芽とわき芽の違いを正しく理解しよう
きゅうりを育てるうえでよく出てくる言葉に「芽」や「わき芽」という表現がありますが、これらは似ているようで役割が大きく異なります。正しく理解して管理することで、実つきや収穫量に差が出るため、初心者こそ知っておきたい知識です。
まず、「芽」とは、苗から新しく伸びてくる生長点のことを指します。主につるの先端部分からぐんぐん伸びていく主軸がこの芽です。この芽が成長して葉や花、そして実をつける軸になりますので、基本的には切り取ったり摘んだりする必要はありません。むしろこの部分が弱ると全体の生育が止まってしまう可能性があります。
一方、「わき芽」は、主軸の葉の付け根から斜めに出てくるつるのことを指します。わき芽は子づるや孫づるとも呼ばれ、育て方の方針によっては摘み取る必要があります。特に、栄養が分散してしまうのを防ぐために、最初のうちはわき芽を摘むことが推奨されます。摘芯や誘引とあわせて、バランスよく育てることがきゅうり栽培では非常に重要です。
このとき注意すべきなのは、成長段階に応じて「どのわき芽を残して、どのわき芽を取るか」を見極めることです。例えば、最初の数節まではすべて摘み取り、中段以降のわき芽は1〜2節で摘芯して実をつけさせるなど、きゅうりの姿を整えながら収穫量を調整することができます。
前述の通り、主軸を間違って摘んでしまうと、全体の成長が止まってしまうことがあります。そのため、「芽」と「わき芽」の違いを正しく理解することは、育て方の精度を大きく左右する要素になります。
このように考えると、きゅうりの管理は単に「育てる」だけでなく、「育ち方を観察して調整する」ことが求められる作業だと言えるでしょう。芽とわき芽の違いを理解していれば、よりスムーズに健康な株に育てることができます。
きゅうりの育て方におけるわき芽処理と摘芯のやり方

- きゅうりのわき芽はどれを取ればいい?見分け方の基本
- きゅうりの芽かきはどこまですればいいのか?
- きゅうりのわき芽はいつ取るのが適切か?
- 花がついたきゅうりのわき芽をどうするか?正しい処理方法
- きゅうりにわき芽が出ない原因と対策
- きゅうりの摘芯の仕方を図解でわかりやすく紹介
きゅうりのわき芽はどれを取ればいい?見分け方の基本
きゅうりを育てていると、主軸から出てくる無数のつるを目にするようになります。これが「わき芽」と呼ばれる部分です。きゅうりのわき芽は、どれでも取ってしまえばいいというものではなく、栽培の目的や育てる環境に合わせて、取るべきわき芽と残すべきわき芽を見分ける必要があります。
まず、基本的な考え方として、わき芽とは主軸(親づる)の葉の付け根から斜めに伸びてくる子づるのことです。苗がまだ小さいうちは、体力が十分でないため、成長に必要な栄養を主軸に集中させることが大切です。この時期に余分なわき芽が伸びると、栄養が分散してしまい、主軸の伸びが鈍くなってしまいます。そのため、下から数節(通常は5節くらいまで)に出るわき芽は、基本的にすべて摘み取ってしまうのがよいとされています。
一方で、苗がしっかり根付いてつるが伸びてきた中盤以降は、わき芽をすべて取ってしまうと、収穫できる実の数が減ってしまう可能性があります。このタイミングでは、すべてのわき芽を取り除くのではなく、一部を残して2〜3節目で摘芯し、実をつけさせる「側枝利用」の方法が効果的です。
見分け方のコツとしては、まず主軸と葉の間から出ている小さなつるを見つけることです。最初は非常に小さく、放っておくとすぐに伸びて葉を出し始めます。葉が数枚ついてしまう前に早めに取り除くのが理想です。手でつまんで軽く折るか、清潔なハサミで切り取りますが、無理に引きちぎると株を傷めることがあるため、力加減には注意が必要です。
わき芽を取る目的は、株の形を整え、風通しと日当たりを確保することにあります。特に密植した場合や、プランターで栽培しているときは、わき芽を適切に管理しないと病害虫の発生原因にもつながります。
このように、どのわき芽を取るかは、時期と全体のバランスを見ながら判断する必要があります。すべてを取ってしまうと実の数が減り、放置しすぎると株が弱るという両極端な結果になるため、目的に応じた見極めが大切です。
きゅうりの芽かきはどこまですればいいのか?
きゅうりを育てる中で「芽かき」という作業がありますが、これはわき芽の処理とも関係しています。芽かきとは、きゅうりの茎の節から出てくる不要な芽やつるを取り除く作業のことです。ただ、どこまで取れば良いのか悩む方も多く、やりすぎてしまうと逆効果になることもあります。
芽かきの範囲を決めるうえで大事なのは、「きゅうりの成長段階」と「育てる目的」をきちんと把握することです。例えば、家庭菜園で育てていて、実をたくさん収穫したいという目的がある場合は、芽かきをしすぎない方が良いケースもあります。というのも、芽かきによってわき芽を完全に除去してしまうと、実がつく部分も減ってしまうからです。
一般的には、苗を植えてからつるが伸び始める初期の段階では、地表から数えて5節目くらいまでの芽かきが推奨されています。この部分のわき芽は、株の基盤ができていない状態で伸びてくるため、残しておくと主軸の生長が遅れがちになります。主軸をしっかり育てるためにも、初期段階の芽かきは忘れずに行いたい作業です。
中盤以降になると、主軸が安定して伸びてくるため、すべてのわき芽を取る必要はなくなります。むしろ、わき芽を適度に残して実をつけさせたほうが、収穫量は安定します。ただし、残す場合でも無制限に伸ばすのではなく、2〜3節程度で摘芯するのが一般的です。この方法なら株全体のバランスを保ちつつ、管理もしやすくなります。
また、芽かきをする時間帯にも注意が必要です。日中の暑い時間帯に作業をすると、切り口が乾きにくく病原菌が入りやすくなるため、朝のうちに行うのが理想的です。ハサミを使う場合は、消毒をしてから使うことで病気のリスクを下げることができます。
このように、きゅうりの芽かきはやればやるほど良いわけではなく、時期や目的に応じて調整する必要があります。どこまでやるかを見極めながら、植物のサインを観察する力を養っていくことが大切です。
きゅうりのわき芽はいつ取るのが適切か?
きゅうりのわき芽を取る作業には、適切なタイミングがあります。間違った時期に取ってしまうと、株に負担をかけてしまい、かえって成長を妨げてしまうことがあるため、タイミングの見極めは重要です。
わき芽を取るべきなのは、苗を植えた直後から本葉が4〜5枚ほどになった頃が目安です。この時期、根の成長と茎の伸びが本格化し始めるため、下の方のわき芽を早めに取り除くことで、主軸に栄養を集中させることができます。あまり早くにわき芽を取ると、まだ十分に伸びていない茎を傷つける可能性があるため、ある程度成長してから行う方が安全です。
特に重要なのは、根元から5節目くらいまでに出るわき芽です。この部分のわき芽は、栄養を吸い取ってしまう割に、実がうまくつかないことが多いため、できるだけ早めに取り除いておく方が効果的です。ここまでのわき芽処理は、「初期管理」として、きゅうり栽培の成功に直結します。
ただし、成長が進んで中段以降に入ったわき芽については、むやみに取り除く必要はありません。この時点では、わき芽から出る側枝にも実がつく可能性があるため、必要に応じて摘芯しながら利用するのが効率的です。つまり、「わき芽を取る時期」は成長段階によって変える必要があるのです。
天候や気温によっても、わき芽を取るタイミングには微調整が必要になる場合があります。例えば、雨が続いて湿度が高い日は、わき芽を放置すると病気が広がりやすくなるため、風通しを良くする目的で早めに処理することがあります。一方、猛暑日には株にストレスがかかりやすくなるため、剪定のタイミングをずらすことも選択肢になります。
このように考えると、わき芽を取るタイミングは一律ではなく、「きゅうりの状態」「季節」「目的」に応じて柔軟に対応することが求められます。決まった日に作業するよりも、植物の様子を見ながら対応することが、きゅうり栽培を成功させる鍵と言えるでしょう。
花がついたきゅうりのわき芽をどうするか?正しい処理方法

きゅうりを育てていると、わき芽に花が咲いているのを見つけることがあります。これを見て「このまま残して実をつけさせるべきか?」「それとも取ってしまったほうがよいのか?」と迷う人は少なくありません。とくに初心者にとっては、せっかく花が咲いたものを切り取ることに抵抗を感じるものです。
しかし、花がついたからといって必ずしも残すのが正解とは限りません。まず確認すべきは、そのわき芽が株全体のバランスにとって適切な位置かどうかです。たとえば、根元に近い部分に出たわき芽の場合、花が咲いていても摘み取るのが基本になります。これは、根元付近のわき芽は株の成長初期に出ることが多く、主軸や葉への栄養供給を妨げやすいためです。
一方、中段から上にかけて出たわき芽で、なおかつつるの長さや葉の数が整っている場合には、花を咲かせたまま残して実をつけるという選択肢も出てきます。この際に重要なのは、わき芽の伸びすぎを防ぐために2〜3節目で摘芯することです。こうすることで、つるが暴れすぎず、適切な長さで実を育てることができます。
花の種類にも注目しましょう。きゅうりには雄花と雌花があり、実をつけるのは雌花です。見分け方としては、花の根元に小さなきゅうりの赤ちゃんのような膨らみがあるのが雌花です。この膨らみがないものは雄花であり、基本的に実はなりません。雄花がついたわき芽であれば、収穫には直結しないため、早めに摘み取ってしまって構いません。
また、花が咲いているからといって、そのまま放置してしまうと、栄養がそちらに集中してしまい、主軸の成長や他の実の育ちに悪影響を与えることもあります。そのため、わき芽に咲いた花が主軸や他の実にとってどう作用するのかを見極めながら、処理を判断することが大切です。
このように、花がついたわき芽であっても、場所や株全体のバランスを見ながら、摘むか残すかを決める必要があります。「花が咲いたから実ができる」という単純な話ではないという点に注意が必要です。
きゅうりにわき芽が出ない原因と対策
きゅうりを育てているのに、なぜか思うようにわき芽が出てこない——このような悩みを持つ家庭菜園初心者は意外と多いものです。わき芽はきゅうりの収穫量に直結するため、その成長が止まったままだと、実の数が増えず栽培の楽しみも半減してしまいます。そこで、わき芽が出ない原因とその具体的な対策について詳しく見ていきましょう。
まず考えられる原因のひとつは、「苗の生育環境が適切でない」ことです。特に、日照不足は大きな影響を与えます。きゅうりは日光を好む野菜であり、1日に最低でも5~6時間は直射日光が必要です。日照が足りないと光合成がうまく行われず、つるの伸びやわき芽の発生が鈍くなります。プランターで育てている場合は、設置場所を再検討し、できるだけ日当たりの良い場所に移動させましょう。
次に、水やりと肥料のバランスが崩れている可能性もあります。水の与えすぎによって根が酸欠状態になると、地上部の成長が止まってしまうことがあります。また、肥料が多すぎると葉や茎ばかりが大きくなってわき芽が出にくくなる一方、肥料が不足していると全体の生長自体が鈍くなるため、どちらも問題です。元肥は適切に施し、その後は追肥のタイミングを守って与えるようにしましょう。
さらに、極端な気温変化もわき芽の発生に影響します。気温が低すぎると生長が止まり、高すぎてもストレスで発芽が抑えられます。適温は20〜30℃で、夜間の冷え込みが厳しいときは不織布などで保温する工夫が必要です。
病気や害虫も見逃せない要因です。とくにアブラムシやハダニが大量に発生すると、株全体が弱ってしまい、わき芽が出る力を失ってしまいます。葉の裏側などをこまめにチェックして、早めに防除対策を行うことが重要です。
このような原因を一つひとつ確認しながら、育成環境を改善していくことで、わき芽の発生は回復するケースが多いです。わき芽が出ないからと焦らず、まずは株が健やかに育つ条件を整えることが、長い目で見た収穫の成功につながります。
きゅうりの摘芯の仕方を図解でわかりやすく紹介
きゅうりの栽培において、摘芯(てきしん)は欠かせない管理作業のひとつです。摘芯とは、主軸や側枝の先端を切り取ることで、株の生育をコントロールし、実つきを良くする目的で行われます。ただ単に切ればよいというものではなく、どこでどう切るかを理解することが、きゅうりを健康に育て、たくさんの実を収穫するうえで非常に重要です。
摘芯の基本的なタイミングは、主軸が支柱のてっぺんに届いたときです。この段階で頂点をそのまま伸ばし続けると、つるが絡まりすぎたり、株全体に栄養が行き届かなくなるおそれがあります。そのため、主軸が一定の高さに達したら、その先端を切ることで、側枝や孫づるへ栄養を分配させるというのが狙いです。
切る位置は、主軸の先端から1〜2節下がったあたりが適切です。清潔なハサミを使って、斜めにスパッと切り取るようにします。切り口が濡れていたり、汚れていると病気のもとになるため、天気の良い日の午前中に作業を行うのが理想的です。
また、側枝(子づる)や孫づるの摘芯も同様に行います。側枝は基本的に2〜3節で摘芯し、実がつきやすい形に仕立てます。こうすることで、株全体の風通しが良くなり、光が全体に行き渡りやすくなります。特にプランター栽培などでスペースが限られている場合には、摘芯の効果がより大きく表れます。
前述のような剪定作業は「整枝」とも呼ばれ、摘芯と併せて行うと一層効果的です。整枝によって無駄な葉やつるを取り除くことで、害虫の発生を抑えたり、実の生長を早めたりすることができます。
摘芯は初めての人には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、図解や写真を参考にしながら、少しずつ試していけばすぐに慣れてきます。逆に、まったく摘芯をせずに放置すると、つるが絡まりすぎて管理しづらくなり、収穫量にも悪影響が出ることがあるため、避けたほうがよいでしょう。
このように、きゅうりの摘芯は「適切な位置」「適切な時期」に「清潔な方法」で行うことがポイントです。図や写真を併用しながら、実際の生長の様子に合わせて柔軟に対応していく姿勢が、うまく育てるための鍵となります。
以下に、それぞれの箇条書きをやや長めの文に修正し、「きゅうりの育て方とわき芽の管理」をより具体的に理解できるようまとめ直しました。語尾は「だ・である調」で統一し、文末に句点は付けていません。
きゅうりの育て方とわき芽の管理を成功させるための総まとめ

- きゅうりは非常に成長が早いため、毎日の観察とこまめな手入れが欠かせない
- 植え付けの時期は気温が安定する5月上旬から中旬で、遅霜が完全になくなった頃が最適である
- 生育には強い日光が必要であり、1日5〜6時間以上の日当たりを確保することが望ましい
- 根の張りが浅いきゅうりには、排水性と保水性のバランスが取れた土づくりが重要になる
- プランターで育てる場合は、深さ30cm以上かつ容量20L以上の大型タイプが推奨される
- プランター栽培では水切れしやすいため、特に夏は朝と夕方の2回水やりを行うのが効果的である
- 一本立ての支柱はスペースを取らず管理もしやすいため、初心者には取り入れやすい方法である
- ただし、一本立ては風雨に弱いため、台風や強風時には補助の支柱や固定具で補強する必要がある
- 小学生でも扱えるほど栽培の手順がわかりやすく、自由研究にも向いている野菜である
- じゃがいもやトマトなど、きゅうりと生育条件が合わない野菜は近くに植えないように注意する
- わき芽は株の体力を消耗させないように、生長初期は下の節からこまめに摘み取るのが基本である
- 芽かきは主軸の生長を優先するため、苗の初期段階では下から5節目までを目安に整理するとよい
- わき芽が出ない場合は、日照不足、水のやりすぎ、肥料バランスの偏りなどが原因として考えられる
- 花がついたわき芽はすべて残すのではなく、位置や株のバランスを見て摘むか判断すべきである
- 摘芯は主軸や子づるの先端を整える作業で、栄養を全体に分配しやすくする効果がある
関連記事


